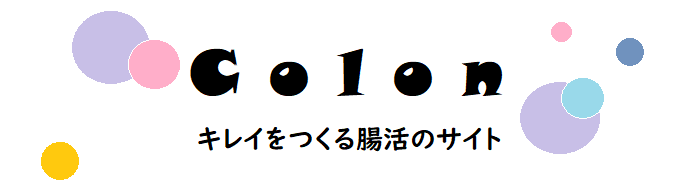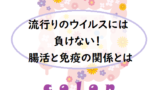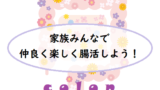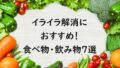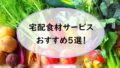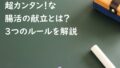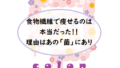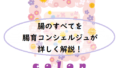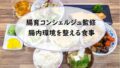ヒトの腸に住む、腸内細菌。その種類は数えきれないくらいといいますが、実際には何種類くらいいるでしょうか?
そして、その腸内細菌たちが身体に与える影響は、具体的にどのようなものなのでしょうか?
この記事では、腸内細菌の種類と役割、そして健康と美容に対する影響についてわかりやすく紹介していきます。
腸内細菌の種類は解明されていない
腸内細菌の種類には、諸説あります。
日本ビフィズス菌センター/腸内細菌学会では「数百種類」、厚生労働省による健康情報サイトでは「約1000種類」と書かれています。ちなみに、Wikipediaでは「3万種類」です。

腸内細菌の代表的な種類
代表的な腸内細菌である、乳酸菌・ビフィズス菌・大腸菌について簡単にまとめました。
乳酸菌の特徴と働き
乳酸菌は、糖を発酵させて乳酸を生成する細菌の総称です。
主に腸内のpHを酸性に保ち、有害な細菌の増殖を抑制する役割を果たします。
乳酸菌は、ヨーグルトや乳酸菌飲料などで摂取することができ、消化吸収を助ける効果もあります。
ビフィズス菌の特徴と働き
ビフィズス菌は、主に大腸に生息する善玉菌の一種です。
ビフィズス菌は、腸内で乳酸や酢酸を生成し、腸内環境を酸性に保つことで悪玉菌の増殖を抑える役割を果たします。
また、免疫機能の向上や便秘の改善にも寄与しています。
大腸菌の特徴と働き
大腸菌は、腸内に存在する細菌の一種で、善玉菌と悪玉菌の両方があります。
善玉の大腸菌は、ビタミンKの生成や腸内の病原菌の抑制に役立ちますが、悪玉の大腸菌は食中毒の原因となることがあります。
腸内のバランスが重要であり、善玉菌が優勢であることが健康維持に繋がります。
「門」で分けると4種類
腸内細菌の分類方法のひとつ、「門」には4つの種類があります。
この4つの門に属する細菌たちで、腸内フローラ(腸内細菌叢)は構成されています。
4つのうち、最優占菌種とされているのが、フィルミクテス門とバクテロイデーテス門です。
4つの門に属する細菌は、全部で数百種類から3万種類になるといわれています。
大きなグループで分けると3種類
腸内細菌の種類は、大きく3つのグループに分けることができます。
腸内細菌の代表的存在である乳酸菌やビフィズス菌は善玉菌です。
悪玉菌には、大腸菌(有毒株)やブドウ菌、ウェルシュ菌などがあります。
いわゆる「痩せ菌」と呼ばれるバクテロイデーテス門の菌は、日和見菌に属しています。
腸内細菌のバランスが健康に与える影響
腸内細菌のバランスと健康の関係について、以下の3つに分けて解説します。
善玉菌と悪玉菌の役割
善玉菌は、消化を助けてビタミンを生成し、免疫力を高める役割を果たします。
一方、悪玉菌は毒素を生成し、腸内環境を悪化させるリスクがあります。
しかし、悪玉菌は肉類などのたんぱく質を分解する働きをするほか、身体の免疫機能を高める役割も担っています。
日和見菌の役割
日和見菌の役割は、腸内細菌のバランスを保つことです。
善玉菌が優勢なときは善玉菌のサポートをし、悪玉菌が優勢なときは同じように身体に悪影響を与える菌になります。
身体に直接的な影響を与えることは少なく、腸内環境の変化によって性質を変えるのが日和見菌の特徴といえるでしょう。
善玉菌を増やすより適度な割合を保つことが大事
多くの人が「善玉菌を増やすことが健康に良い」と考えがちですが、実際には腸内細菌のちょうど良い割合を保つことが重要です。
善玉菌が多すぎても、腸内環境が過度にアルカリ性になることで問題が発生する可能性があります。
逆に、悪玉菌が多すぎると腸内が酸性に傾き、体調不良を引き起こすリスクが高まります。
腸内細菌の適度な割合は、善玉菌2:悪玉菌1:日和見菌7といわれています。
腸内細菌の種類はどうやって決まる?
腸内細菌の増え方や定着の仕方について、3つに分けて解説します。
母親から受け継ぐ細菌
人は、胎内にいる間は腸内細菌をもっておらず、完全な無菌状態です。
初めての腸内細菌は、母親から受け継ぎます。
自然分娩の場合、産道を下りてくる過程で、すでに母体の腸内細菌をうつしてもらっています。さらに、その後の母乳からも細菌を受け継ぎます。
腸内フローラ(腸内細菌叢)が決まる時期
食事や入浴、日常生活で腸内細菌が身体に入り込み、細菌の集合体=腸内フローラが形成されます。
腸内フローラが決まるのは、生後3~5歳といわれています。
腸内フローラは遺伝ではなく、身体に取り込む腸内細菌の種類によって形が異なります。
しかし、親と子は同じ食べ物を食べて同じお風呂に入るといったことが多いため、腸内フローラの形が似るケースが多いです。
無菌・除菌は身体に良くない
完全な無菌はもちろんのこと、過度な除菌も身体に良いことではありません。
なぜなら、適度な菌の存在は免疫機能や消化機能を発達させ、健康を保ってくれるからです。
実際、現代の清潔志向が強い生活環境では、過剰な除菌や抗生物質の使用が腸内フローラのバランスを崩し、結果的に抵抗力の弱い人が増えていると指摘されています。
腸内細菌のバランスは腸活で変えられる?
腸内環境を整える、いわゆる「腸活」が腸内細菌のバランスに与える影響について解説します。
定着した腸内細菌の種類は変えられない
定着した腸内細菌の種類は、変えることはできません。
生まれてからの生活で身体に取り込まれるさまざまな菌は腸内に定着し、腸内フローラを形成します。
形成された腸内フローラは、持ち主である人間の体質や肌質、性格にまで影響をおよぼすといわれています。
ちなみに日本人は、ビフィズス菌とバクテロイデス菌主体で形成された腸内フローラであることが多いそうです。
腸内細菌の数は変えることができる
定着した腸内細菌の種類を変えることはできませんが、特定の種類の細菌を増やしたり減らしたりすることは可能です。
普段の食事や生活習慣を変えれば、もともと住み着いていた悪玉菌の増殖を抑え、善玉菌を増やせます。
また、無理のない腸活を続けていくことで善玉菌優勢の腸内フローラが維持され、健康や美容に良い影響をもたらします。
腸内フローラを整える食品
腸内フローラを整える食品について、大きく2つに分けて紹介します。
発酵食品の効果
発酵食品は、腸内フローラを整えるために非常に効果的です。
代表的な発酵食品の種類と役割は、以下のとおりです。
共通点は、善玉菌を多く含む食品である点です。
善玉菌を含むこれらの食品を摂取することを、プロバイオティクスといいます。
食物繊維を多く含む食品の効果
食物繊維は、腸内フローラのバランスを維持するために欠かせない成分です。
食物繊維には2つの種類があり、それぞれ、以下の役割があります。
また、食物繊維は腸内で発酵され、短鎖脂肪酸という物質を生成します。
短鎖脂肪酸は腸内のpHを低下させ、悪玉菌の増殖を抑える効果があります。
このように、腸内で善玉菌をサポートする食品を摂取することを、プレバイオティクスといいます。
まとめ
腸内細菌の種類は、現代の医学でも完全に解明されてはいません。
その中でわかっているのは、以下の3点です。
風邪をひきづらい丈夫な身体、太りにくい身体、トラブルが少ない強い肌、ストレスをためないメンタル、それらは腸内細菌の数をコントロールすることで手に入れられます。
腸内フローラを整える生活を意識し、健康で美しい身体をキープしましょう。